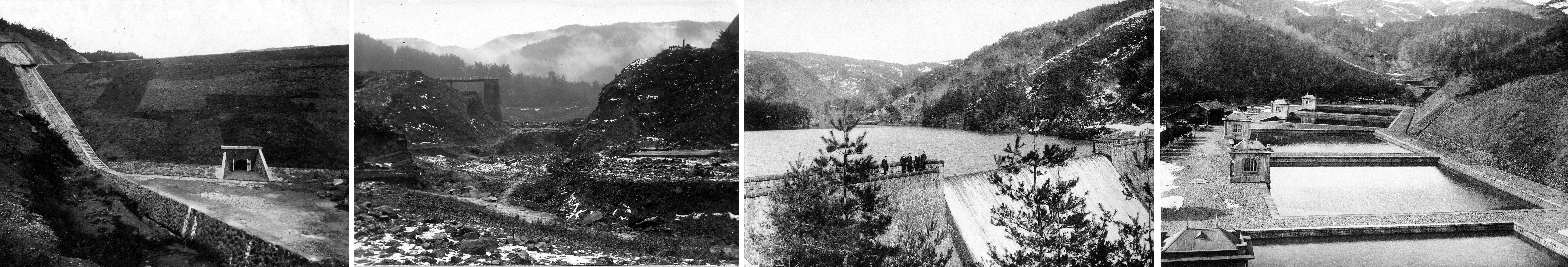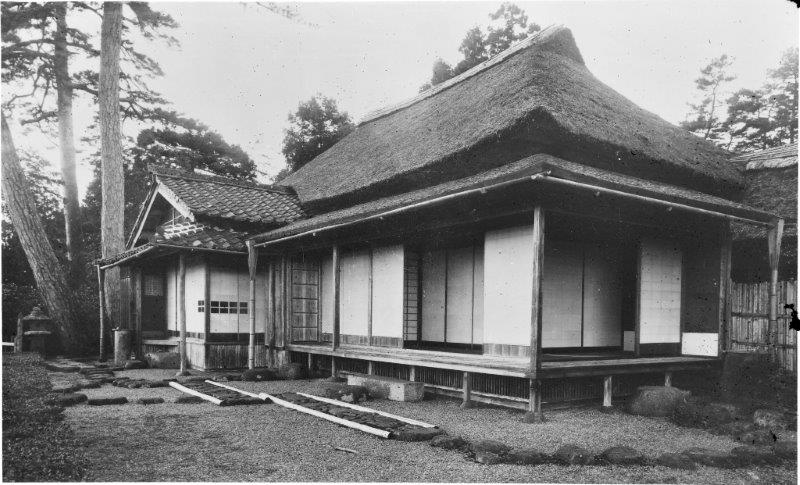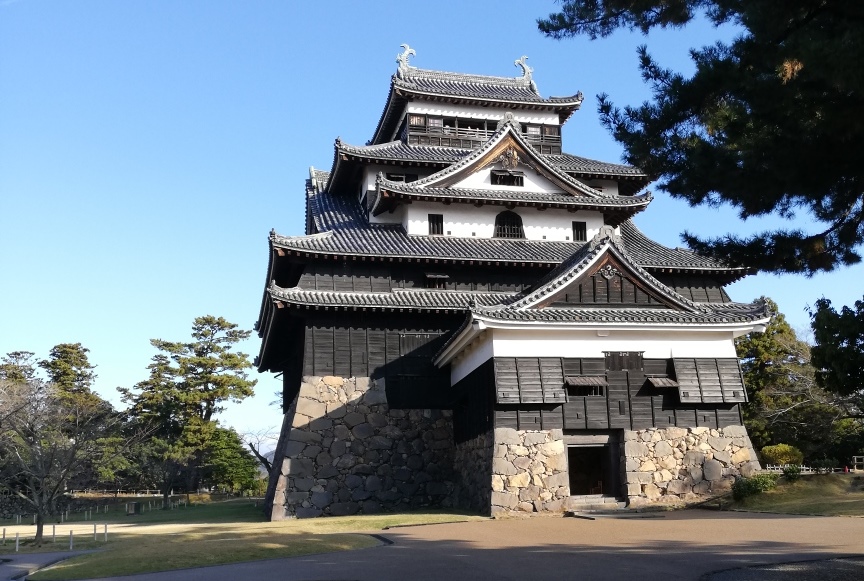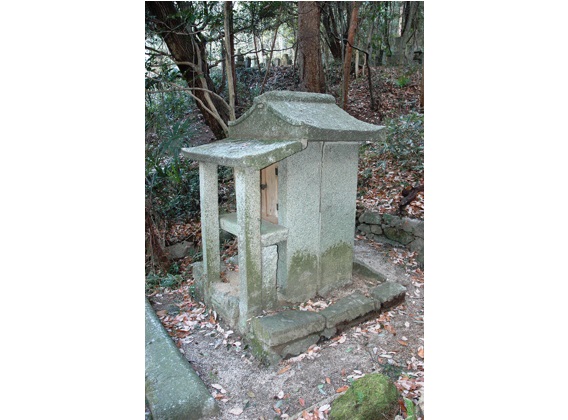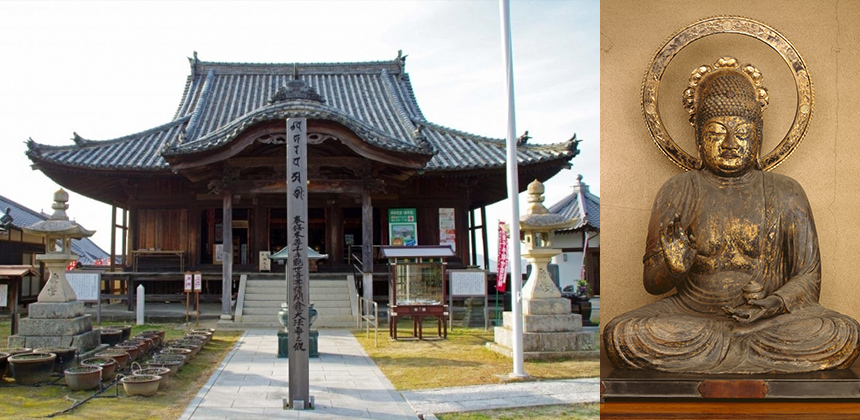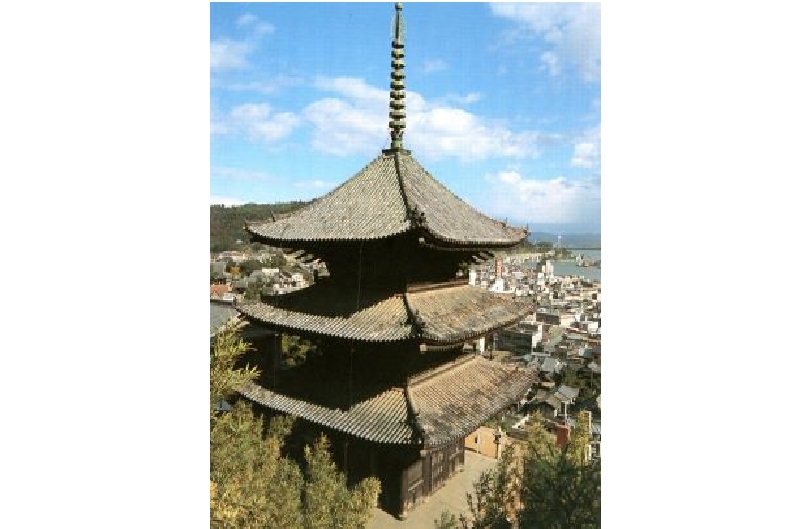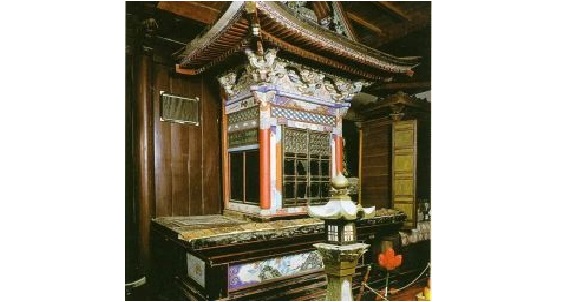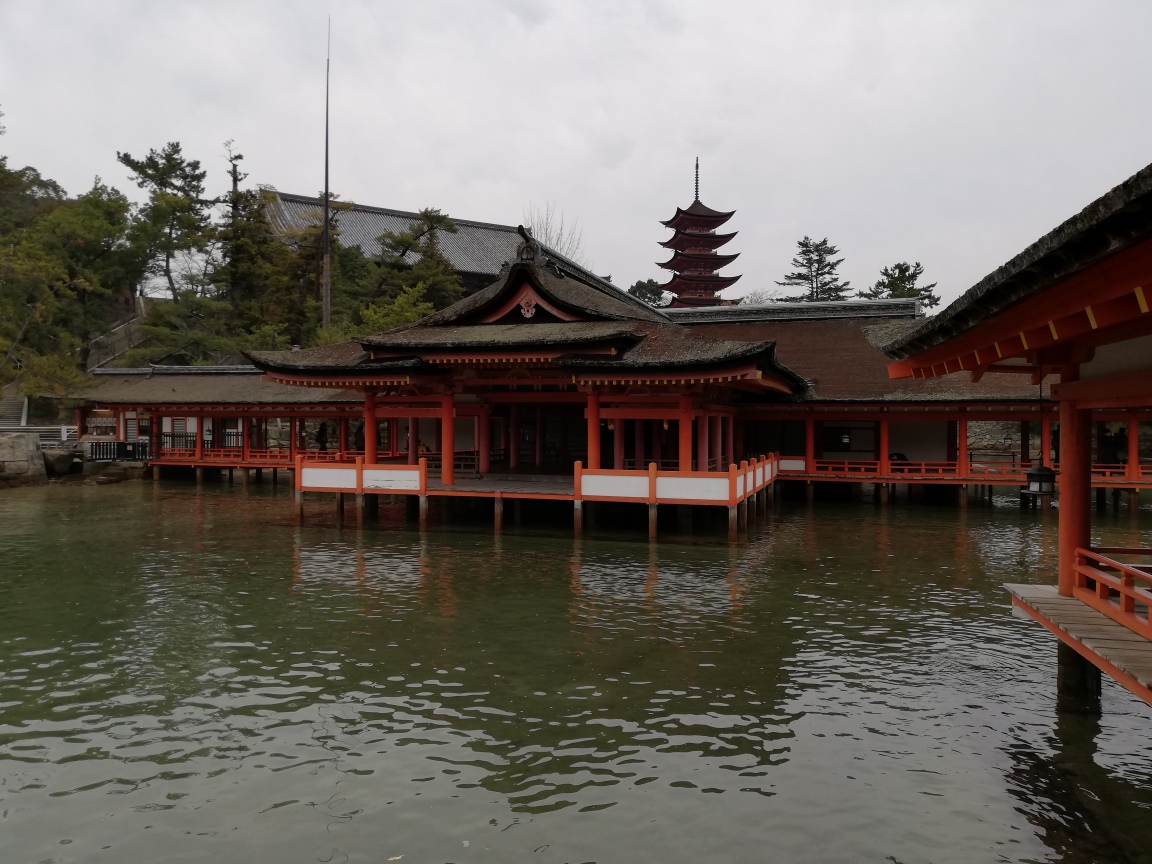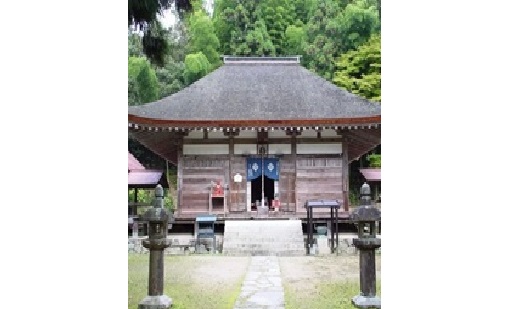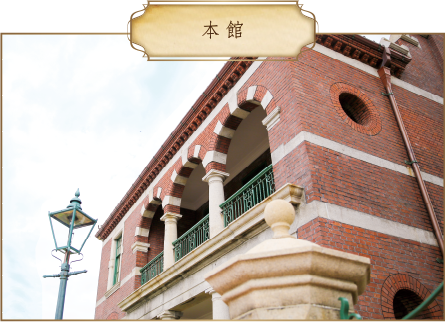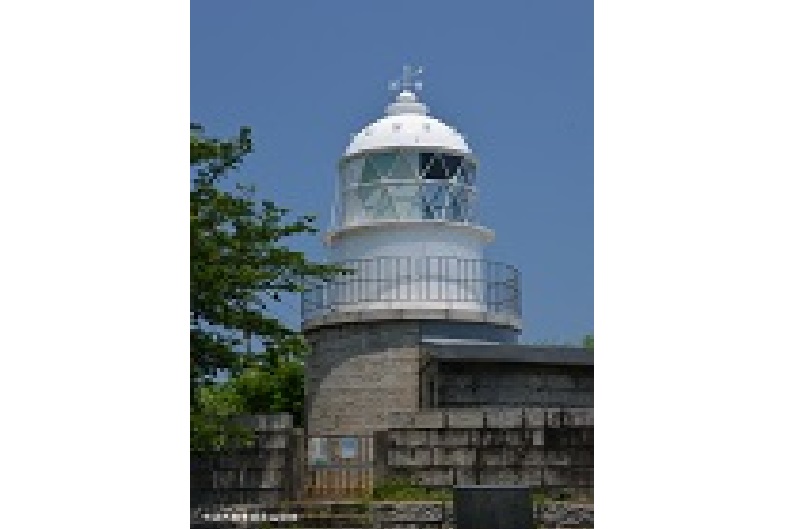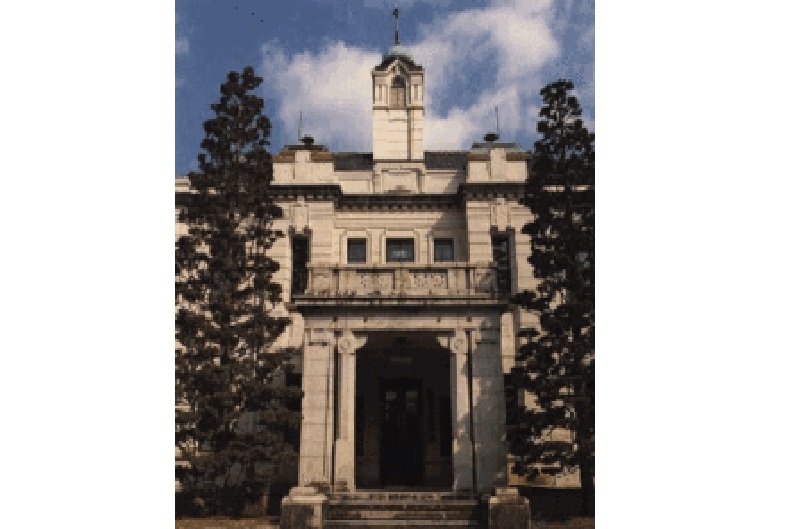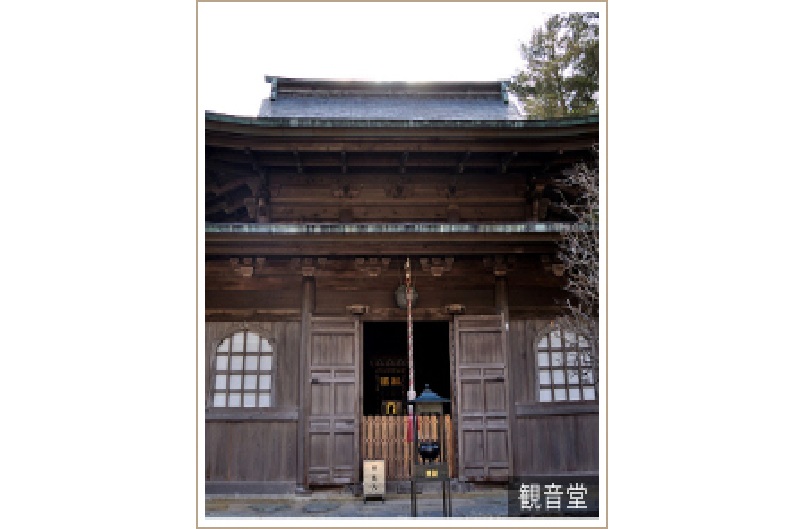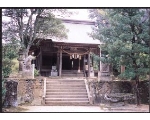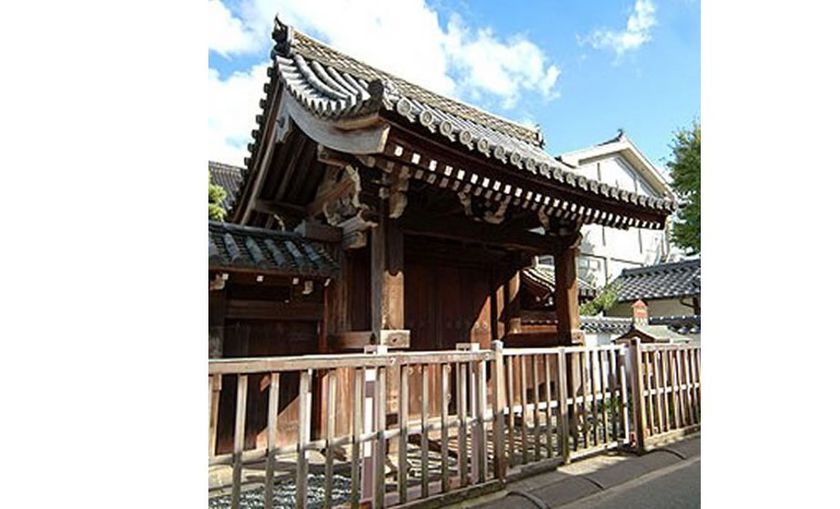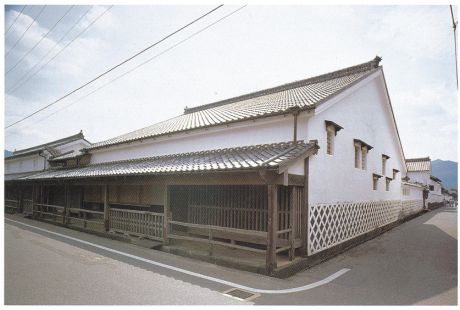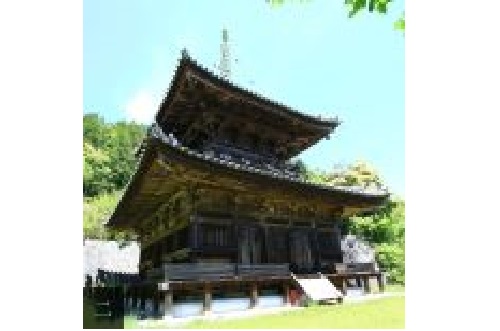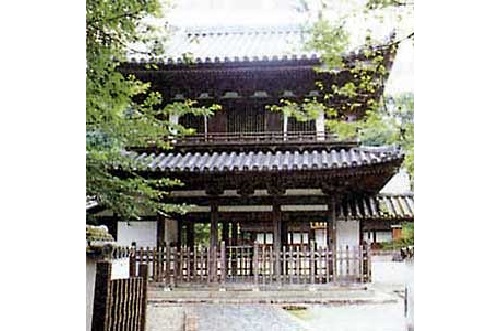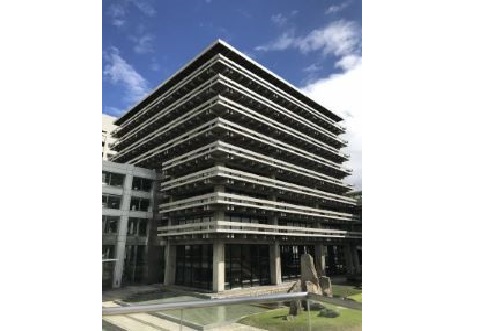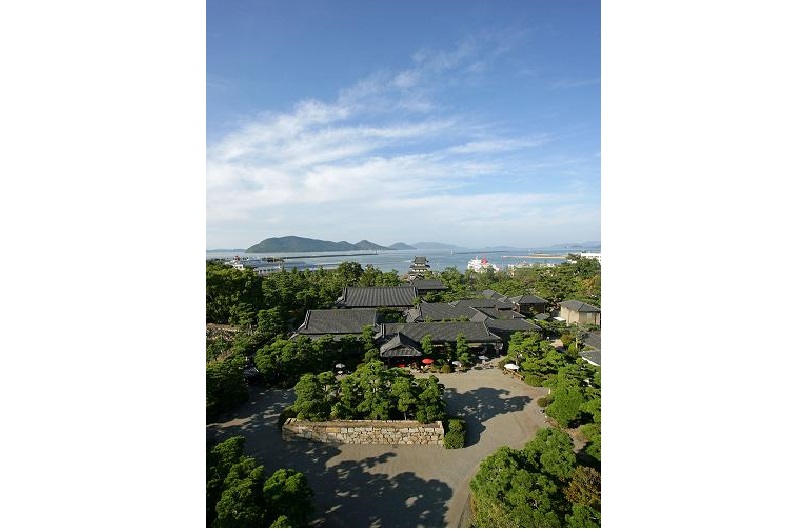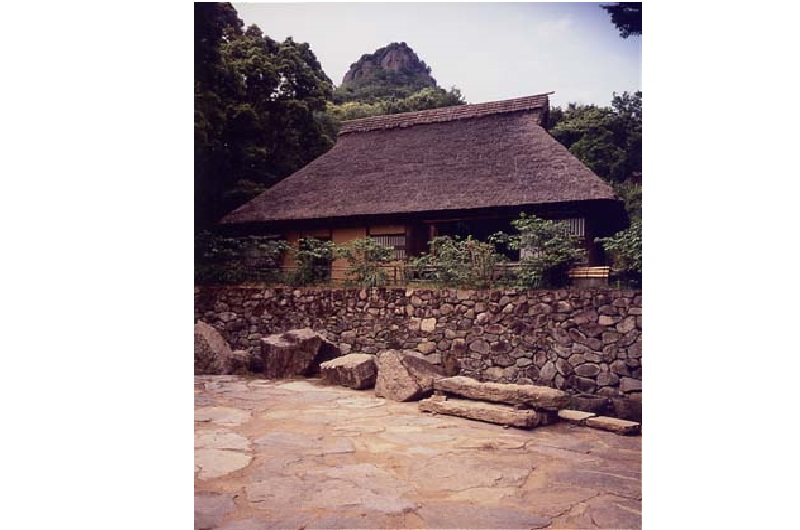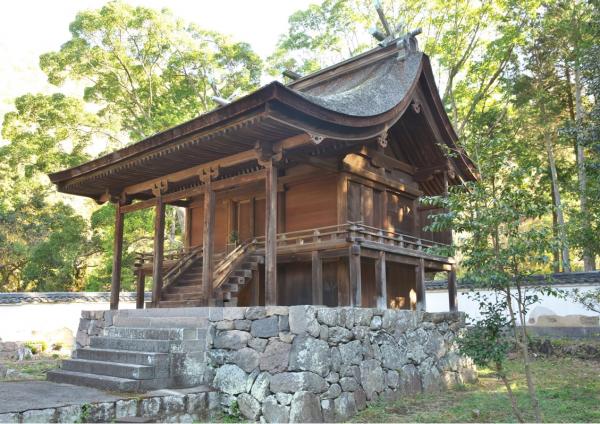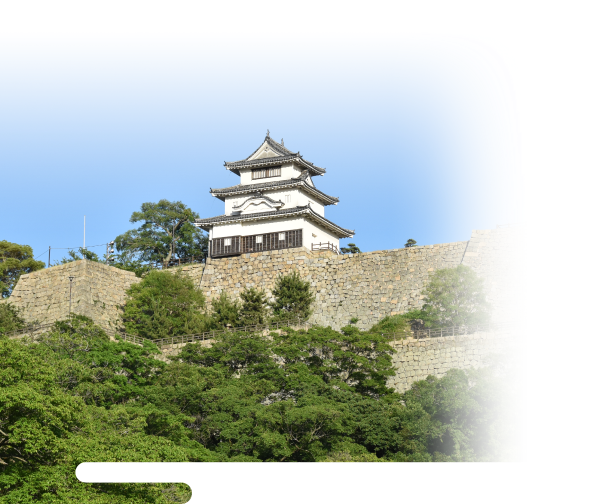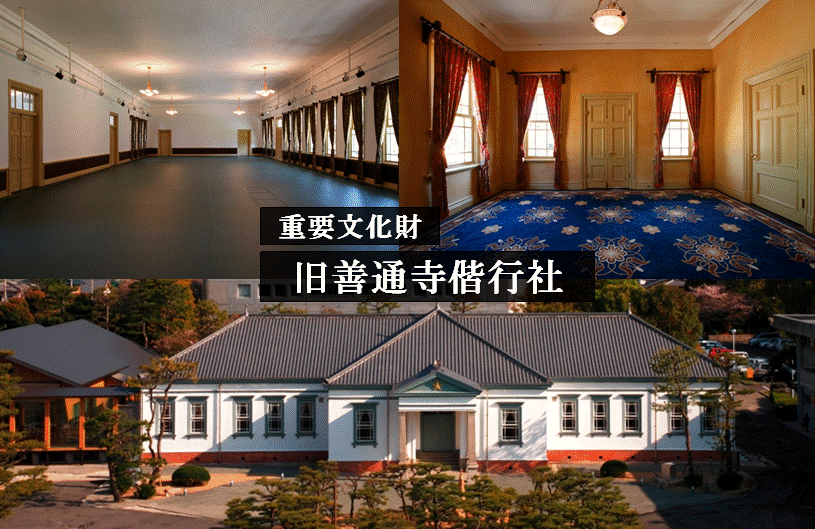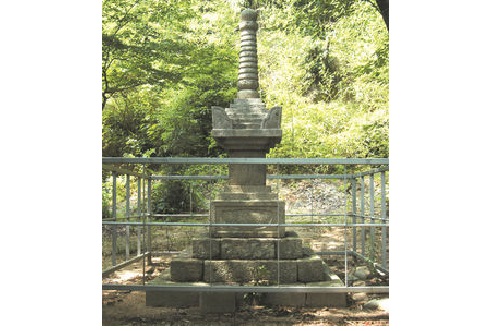■住所
GoogleMap
島根県仁多郡奥出雲町上阿井1655番地
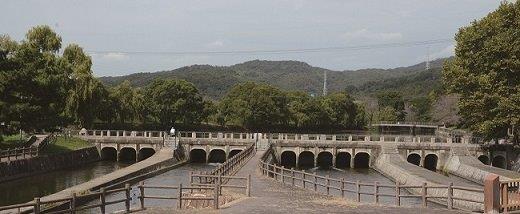




■住所
GoogleMap
徳島県板野郡上板町佐藤塚三三五番地