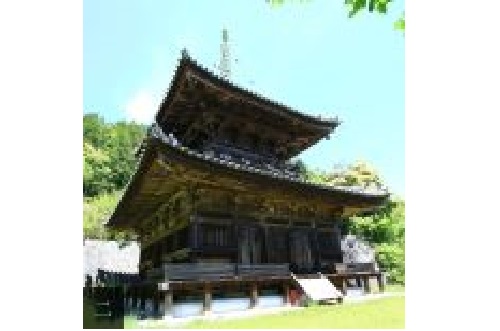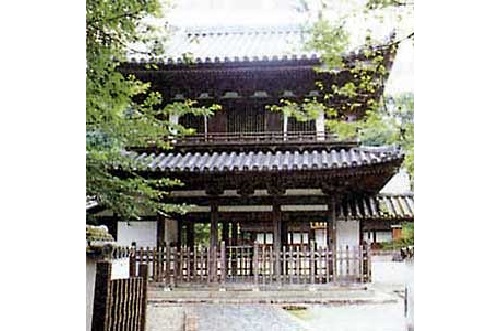史跡検索
徳島県 重要文化財建造物(18件)

■住所
GoogleMap
徳島県板野郡上板町佐藤塚三三五番地
■概要
江戸時代からこの地域で藍作を営み、明治中期には有数の藍商として繁栄した戸田家の住宅で、1886年(明治19年)頃に建て替えられ、現在の屋敷地の骨格が整えられました。その後、1937年(昭和12年)には質の高い接客空間として東座敷が建築されました。 石垣で高めた敷地を中心に、主屋、土蔵群、藍を寝かせる「藍寝床」などが配置されており、近世以来の伝統的な藍屋敷の全体構成を残しています。一方で、二階を居室にした主屋や、別棟の東座敷には近代的な特徴も見て取ることができ、明治から昭和にかけて最盛期を迎えた藍商の繁栄ぶりを伝える貴重な建物として評価されています。
■戸田家住宅の重要文化財建造物